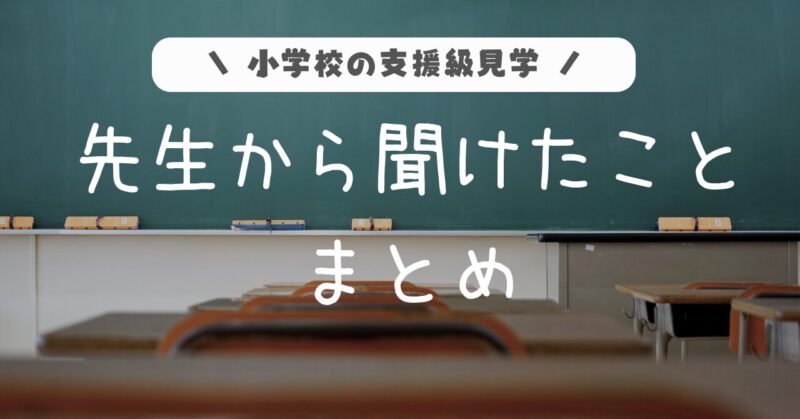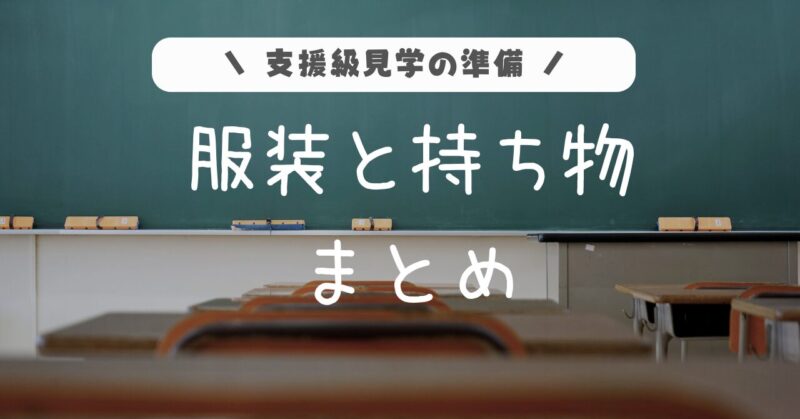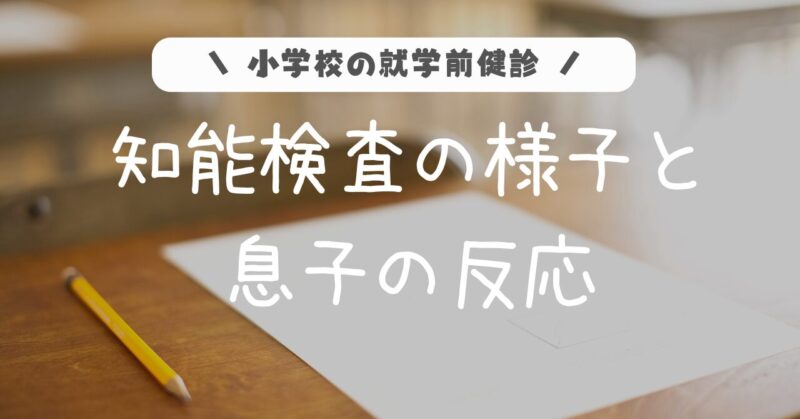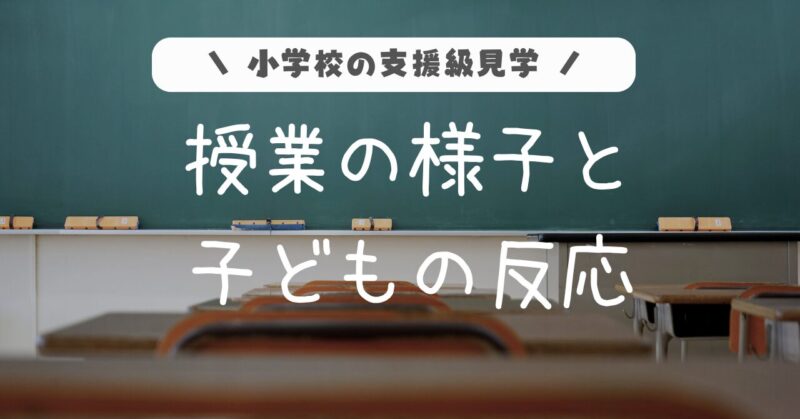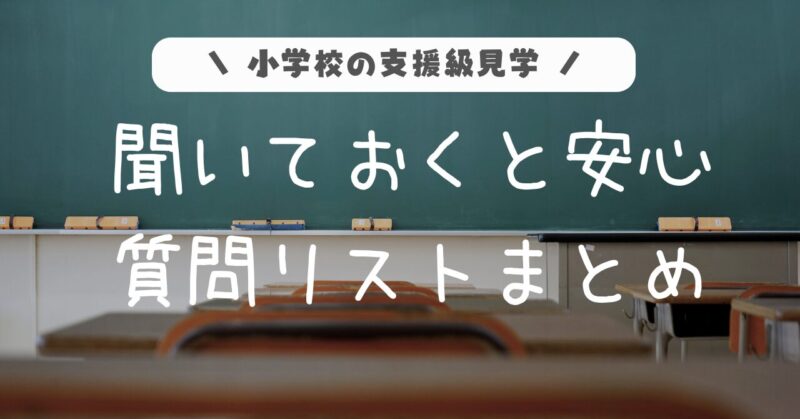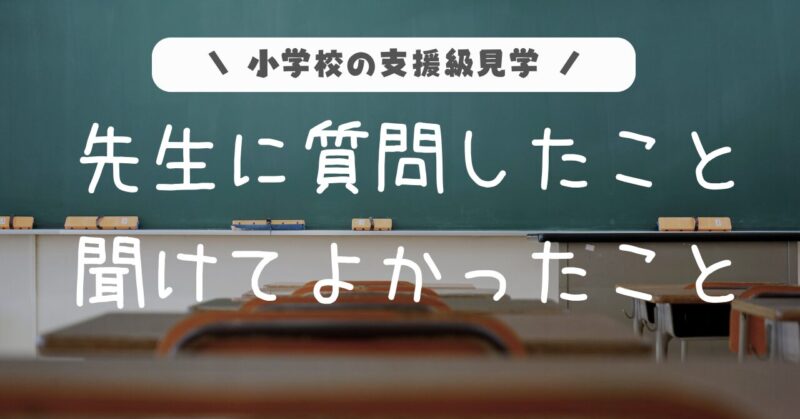就学相談のスケジュールと必要書類まとめ|支援級を希望するまでの流れも紹介
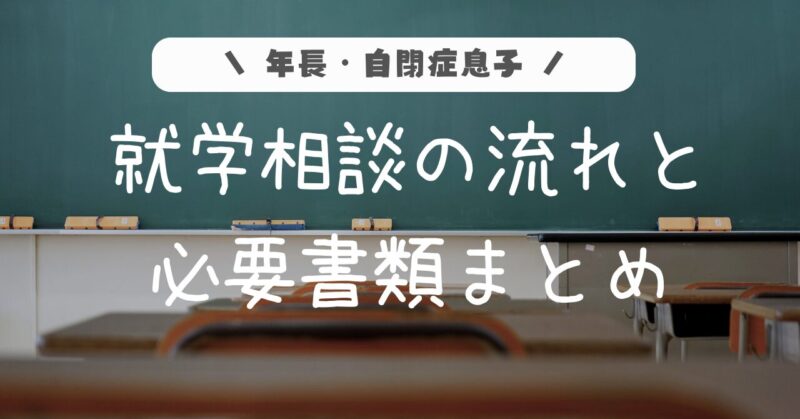
今年、年長の息子は知的障害のない自閉症スペクトラムと診断されています。
春に障害福祉課の職員さんとお話ししたときに、「就学へ向けてどう考えていますか?」と聞かれ、支援級を検討していることを伝えました。
その際に初めて、就学相談の時期や流れを知ることになり、「夏には動き始めますよ」と言われて、思ったより早くて驚いたのを覚えています。
この記事では、我が家の経験をもとに、就学相談のスケジュールや準備、必要書類についてまとめています。
自治体によって多少の違いはあると思いますが、参考のひとつになれば嬉しいです。
早めの相談をおすすめする理由
就学へ向けたスケジュールは、思っている以上に早く動き出します。
書類や知能検査の準備も必要で、動くのが遅れると、申し込みに間に合わない可能性もあります。
特に注意が必要なのは、困り感や集団生活への不安はあるけれど、まだ支援に繋がっていない場合や発達の病院を受診していない場合です。
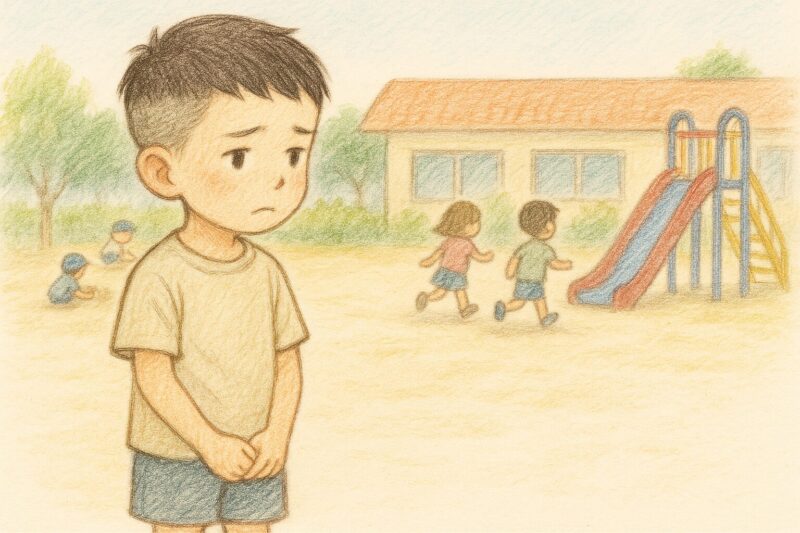
うちの息子は集団に入るのが苦手で、幼稚園で不安そうな表情で過ごしていることがよくありました。
受診に繋がっていない場合は、判定会議の前に指定された医師の診察を受けたり、自治体で発達検査を受けることができるそうです。
ただ、そのための日程調整が必要になるので、できるだけ早めに動き出すことをおすすめです。
どこに相談すれば良いの?
相談先は自治体によって違いますが、まずはお住まいの役所の福祉課や教育委員会に問い合わせてみるのがおすすめです。
「就学へ向けての不安があること」「就学相談について話を聞きたいこと」を伝えれば、流れや必要なことを教えてもらえると思います。
また、集団での様子を知っている保育園や幼稚園の先生に相談しても良いと思います。
すでに療育施設や発達外来に通っている方は、そちらのスタッフさんに
「そろそろ就学のことを考えた方が良いですか?」
「〇〇さんから見て、どう思いますか?」
と、客観的意見を聞いてみるのもおすすめです。
就学に向けたスケジュール
福祉課の職員さんから、就学に向けた大まかな流れを教えていただきました。
我が家の住む自治体の場合は、次のようなスケジュールになっていました。
- 夏休み前後:希望者は学校見学へ
- 秋までに:必要な書類を揃えて提出、知能検査
- 11月~12月:保護者の意思確認の面接、判定会議
- 12月:就学先(在籍学級)が正式に決定
自治体によって多少の違いはあるかもしれませんが、だいたい年長の夏から動き出し、冬に就学先が決まる流れになることが多いようです。
在籍する学級の決まり方
福祉課の職員さんからは、小学校でどの学級に在籍するか の決まり方についても説明がありました。
- 保護者の意向が最も反映される
→ どんなに困り感があっても、保護者が「普通級」を希望すれば普通級に在籍になる。 - ただし希望通りにならない場合もある
→ 保護者が「通級」や「支援級」を希望しても、判定会議での判断によって普通級になることもある。
判定会議では、病院の先生の意見書や幼稚園からの記録をもとに話し合いが行われるとのことでした。
最近は通級や支援級を希望する家庭が増えていて、困り感の強い子が優先されると聞きました。
息子は一見すると「大人しい子」に見えるため、困り感が伝わりにくいのではないか…と、親として心配な気持ちが残りました。
保護者の意思確認の面接って?
判定会議の前に、「どの学級に在籍を希望しているか」を保護者に最終確認する場とのことでした。
自治体によって違いはあるかと思いますが、我が家の自治体では、小学校の校長先生と保護者が面談するという流れでした。
知能検査って何をするの?
就学相談で使われる知能検査は、入学前に小学校で行われる就学時健診で行われる知能検査とは別のものです。
「WISC(ウィスク)」や「WPPSI(ウィプシ)」という検査が使われることが多く、年齢によって使い分けられます(WPPSIは未就学児向け、WISCは小学生以降に多いです)。
子どもの「得意不得意の凸凹」を数値で見える化できるのが特徴です。
息子も、年中の3月に「WPPSI-Ⅲ ウィプシ3」を受けました。
そのため、就学相談の前にあらためて検査を受ける必要はありませんでした。
「1年以内に受けているので大丈夫」と言われましたが、そのあたりの判断は自治体によっても違う場合もあると思います。
知能検査の結果は、就学の判定会議での大切な判断材料にもなるとのことで、判定会議の前に実施するケースが多いようです。
就学の判定会議に必要な書類
就学相談へ向けて揃える書類は、以下の3種類でした。
- 保護者が書く書類(生育歴など)
- 幼稚園の先生が書く記録(我が家の自治体では福祉課の職員さんが幼稚園の先生へ依頼してくれました)
- 発達の病院の先生が書く意見書
病院の先生に書いて頂く意見書は、我が家は定期受診の際にお願いしました。
ちょうど、用紙を受け取ってからすぐに診察があり、早い段階で書いて頂くことができました。
病院によっては、予約がすぐ取れなかったり、書いて頂くのに時間がかかる場合もあるので、余裕を持って準備するのが良いかと思います。
書くのが大変な「生育歴」書類整理のちょっとした工夫
就学に向けた書類の中には「生育歴」を書く欄があり、赤ちゃんの頃からの発達の様子を振り返る必要がありました。
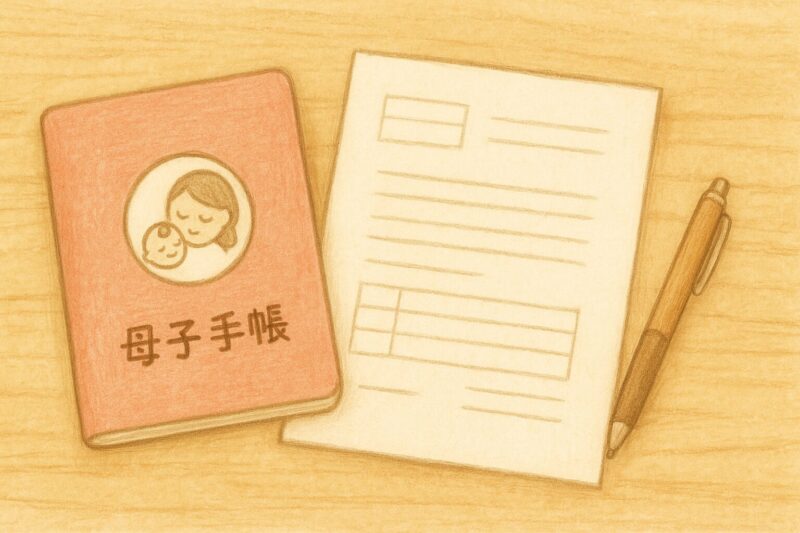
発達障害の子がいると、書類を書く機会が多く、そのたびに母子手帳や昔の日記を見返しながら書くのはすごく手間ですよね。
私が普段からやっている工夫は、発達に関する書類を書いたら、その内容をスマホで写真に残しておくこと。
アルバムの中に「発達関係の書類」というフォルダを作ってまとめているので、あとで必要になったときにすぐ見返せます。
今回の就学に関する書類も、提出する前に写真で残しておきました。
次の相談や別の場面でまた必要になったときにも役立ちます。
同じように就学書類を準備される方には、“提出する前に写真保存” がとてもおすすめです。
まとめ
就学相談は想像以上に早く、そして意外と書類の準備や検査などが多いです。
年長の春から秋にかけて、親としてもかなり動く期間になるので、早めの相談・情報収集が大切だと感じました。
同じように支援級などを検討されている方にとって、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
▷ 支援級の見学・相談・準備をまとめたページはこちら